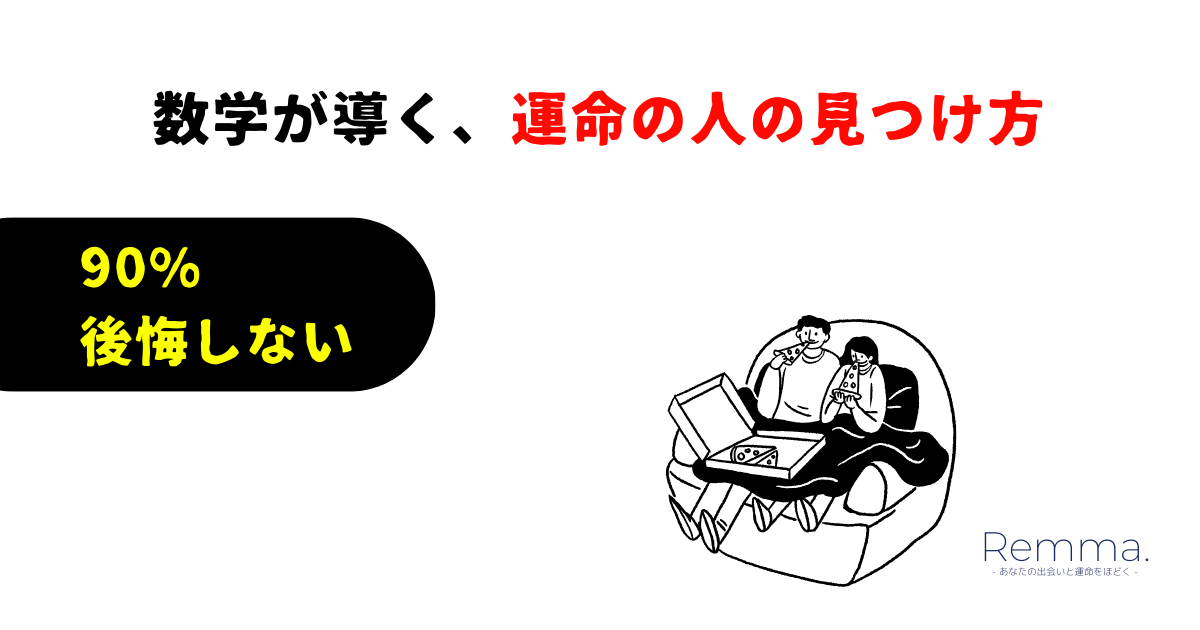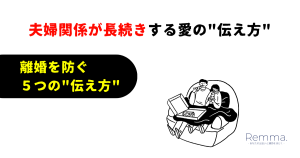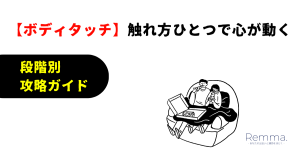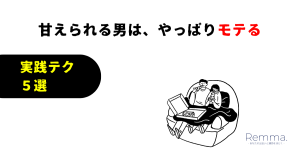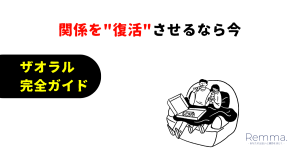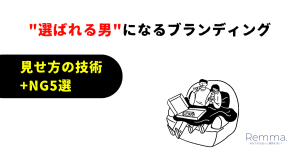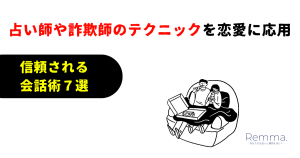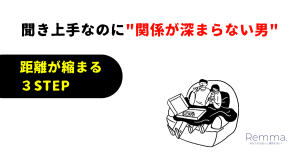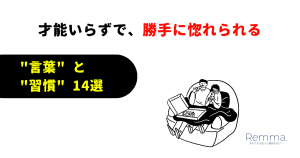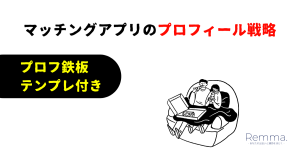「どうすれば自分にとって最適な結婚相手を選べるのか?」
「誰と結婚すれば幸せになれるのか?」
「どんな人を結婚相手にしたら幸せになれるのだろう?」
「幸せな結婚生活を送る為にはどうしたらいいんだろう?」
そんな疑問を抱えている人にとって、この記事は大きなヒントになるはずです。
マッチングアプリや恋愛、さらには転職や引っ越し先の選定にまで応用できる、ある“理論”があります。
その名も、最適停止理論(Optimal Stopping Theory)。
一見難しそうなこの理論、実はたったひとつのルールを守るだけで、90%の確率で理想に近い選択ができるとされています。恋愛に迷う人、特にマッチングアプリを使っている人にとっては、試してみる価値のある知的アプローチです。
恋愛に“公式”があった!90%の確率で理想の相手に出会える方法とは?
結婚前に最適な相手を見つける為にはどうしたら良いでしょうか?
この疑問に対して、数学的に回答を出したのが『最適停止理論』というもので、これに則って相手を見つけると、90%の確率で最適な相手を見つけることができるそうです。
恋愛に当てはめると、「誰と付き合えばベストなのか?」を判断するための明確なルールを与えてくれます。
恋愛に応用できる!最適な相手を見つけるシンプルな手順
恋愛でこの理論を使う方法は、以下の通りです。
- まず、最終的に何人と出会う可能性があるかを予測する。
例えば、マッチングアプリを使って「25人くらいと会うかもしれない」と仮定する。 - その出会い人数の平方根を計算する。
25人なら、平方根は「5」。 - 最初の5人とは無作為に会って“比較材料”をつくる。
この5人とは付き合わずに相手のことを知っていきます。
目的は「誰が一番良かったか」「最良の1人か」を知るための比較ベンチマークを得ること。 - その後、6人目以降で「比較対象の中で一番良かった人」を少しでも超える相手に出会えたら、即決する。
その人があなたにとって最も相性がいい人が現れたら「お付き合いする」「結婚する」といった理論です
これが最適停止理論の基本的な使い方。数学的には、これで約90%の確率でベストな相手を選べると言われています。なので、結婚相手を見つける際は、この理論に従ってこの方法で見つけましょう。
最初の5人は色々な人と出会って、食事に行ったり会話をしたり、あるいは床をともにします。そうやって経験値を積みながら、そのなかであなたにとって「最良の1人」を決めます(付き合ってはいけません)。
6人目以降は総合判断なので例えば「最良の人」より、高スペックではない(すごく美人ではない)けど「最良の人」より優しくて、何より自分を愛してくれる人 だった場合には運命の人かもしれません。
イメージとしては25回のデートをこなすつもりで会って早いと6人目から「本命」に辿り着けるので思ったより、費やす時間が少なく感じられます
「最良の人」との比較を行わなかったり、「最良の人」をはるかに超える「高スペック」や「すごく美人」等を探し求めてしまうと、あなたが幸せな結婚に到達する確率はどんどん下がっていきます。
恋愛成功率が変わる!最初に決めるべき“人数設定”
この理論の面白い点は、最初に設定する出会う人数が「自由」であること。たとえば「49人と会う」と仮定すれば、平方根は7。最初の7人は比較材料として会い、8人目以降で判断していきます。(一生のあいだでデートできる人数の予想でもいいです)
ここで重要なのは、設定する出会う人数=自分の理想の高さに比例しているという点。
もし「理想が高い」と自覚している人が最初に「4人だけ会う」と決めてしまうと、平方根は2。つまり比較材料が2人だけになってしまうため、理論の成功率が下がってしまいます。
逆に、ストライクゾーンが広い人、条件にあまりこだわらない人は、少ない設定人数でもうまくいく可能性が高いということになります。
マッチングアプリと最適停止理論の相性は抜群
マッチングアプリを使っていて、「何人と会えばいいの?」「いつ決めればいいかわからない」と悩む人は多いはず。この理論は、そんな不安をシンプルに解消してくれる考え方です。
「機械的すぎて恋愛っぽくない」と感じるかもしれませんが、そもそもマッチングアプリ自体が自然発生的な出会いではありません。だからこそ、こうしたロジカルな戦略がむしろ有効なのです。
「もう割り切って、徹底的に戦略的にやってみよう」と思ったとき、最適停止理論は非常に頼れる指針になるでしょう。
愛は“選ぶ”より“育てる”が正解?10年後の満足度が語る真実
「重要なのは、愛する相手を選択することではなく、選択した相手を愛すること」という結論を出した世界の研究があります。
簡単にまとめると、、、
<調査>
1982年、ラージャスターン大学(インド)の心理学者であるウシャ・グプタとプーシパ・シングは、恋愛結婚と取り決め婚(お見合いのようなもの)では、どちらの結婚のほうが満足度が高いかについて調査した
<結果>
・取り決め婚の方が恋愛結婚より、結婚10年後の満足度が大幅に高いことが分かった
・恋愛結婚には、最適なパートナーを見つけたという油断があり「愛する」という行為をサボるというのがある
・一方、取り決め婚では、第三者によってパートナーを決められているので、「この人のことを愛せるようにならなければならない」という努力が働いたためではないかと分析されている
つまりより重要なのは、愛する相手を選択することではなく、選択した相手を愛する努力をすることです。
選択 < 選択後の行動
「結婚はゴールではなく、スタート」とよく言うのはそういうことです。
選択することよりも、選択後どのように振る舞うかが重要で、その選択が正しかったかどうかは判断後の行動によって決まります。
一方で、気をつけなければならないのは、選択を大事にしてしまいすぎると、選択後の行動を疎かにしてしまう傾向があるということです。
恋愛結婚には、最適なパートナーを見つけたという油断があり、「愛する」という行為をサボるというのがある
よく起こりがちなのは、悩むことです。
悩むことは悪いことではありませんが、必要以上に時間を投下してしまう上に、労力が必要です。
選択に時間や労力を使えば使うほど、最適な結婚相手を選択することに対しての比重が高まってしまいます。
そうなると、選択後の行動を疎かにしかねません。
なので、『最適停止理論』に則って選択することで、選択に悩みすぎることを防ぐことができます。
さらに、最適な選択ができる確率が90%と、精度も高いです。
理想が高い人は、「自分に自信をつけること」から始めよう
優しくて、完璧で、思いやりがあって、寛容で、いつも親切で、プレゼントもたくさんくれて——
しかもゴミ出しまで忘れない。
そんな完璧な理想の相手に、あなたが出会える確率はどれほどでしょうか?
ウェブコミック『XKCD』の作者であり、元NASAのロボット研究者でもあるランドール・マンローによれば、
理想の相手に出会える確率は、生涯で約1万回の出会いのうち、たった1回だと言われています。
「理想が高いのに、出会いの数が少ない」と理論は機能しづらい
最適停止理論を使うには、最初に「何人と出会うか」という数を自分で決める必要があります。
ただしここで問題になるのが、理想が高いのに、出会う人数が少ない人の場合です。
たとえば「理想はとても高いけれど、10人くらいしか会えなさそう」となった場合、理論上はうまく機能しづらくなります。なぜなら、理想が高いほど、多くの比較対象が必要になるからです。
また、仮に「理想が高いから100人と出会う!」と決めたとしても、実際に100人と会うのは大きなエネルギーが必要で、途中で疲れてしまうかもしれません。
こうしたズレが生まれる原因のひとつが、「自信のなさ」です。
自信のなさが、理想を高くする
理想が高くなる背景には、しばしば自分に自信がないという気持ちが隠れています。
「自分には足りないところがある」と感じるからこそ、
「相手には、あれもこれも満たしてほしい」と、条件を積み重ねてしまうのです。
一方で、自分のことをしっかり好きでいられる人は、相手に過剰な理想を押しつけません。
多少の欠点があっても「自分がいればうまくやっていける」と思えるため、相手に求める条件も自然と現実的になっていきます。
自信をつけるための、日常のヒント
- 自分が笑顔でいられる時間を大切にする
- 友達と楽しい時間を過ごす
- 自分の好きなことに夢中になる
- 「自分っていいな」と思える瞬間を増やす
たとえば、恋愛でうまくいかなくても、友達と笑い合っている時間に「やっぱりこの自分が好き」と感じられたら、それは大きな財産です。
まずは自分を好きになること。
それが、理想を現実的に調整し、恋愛をもっと軽やかに楽しめる大きな一歩になるでしょう。
恋愛だけじゃない。「最適停止理論」は人生のあらゆる選択に使える
実はこの理論、数学や統計学の分野では「37%最適停止問題」と呼ばれ、意思決定理論の古典的なテーマの一つです。英語では「The Secretary Problem(秘書問題)」や「Marriage Problem(結婚問題)」とも呼ばれています。
恋愛に限らず幅広いシーンで活用できる点にあります。たとえば、こんなときにも応用が可能です。
転職先の企業選び
就職活動において、多くの企業や職種から最適な選択肢を見つけるのは難しい場合があります。この場合、37%ルールを適用することで、効率的に最適な求人を見つけることができます。初めの37%の期間(例:最初の1か月間)で応募先を観察し、情報を収集します。この期間中は積極的に応募せず、企業の情報や仕事の条件を調査します。残りの期間で、最初の37%で得た情報を基に、それらよりも良いと思われる求人に応募します。
引っ越し先の物件選び
最初の37%の物件(例:10件のうち最初の3~4件)は見学するだけにし、契約はしません。この期間中は市場の状況や物件の特徴を理解するために情報を収集します。残りの物件から、最初の37%で見た物件よりも良いと思われる物件を選びます。
購入決定
高価な商品や重要なサービスの購入決定にも37%ルールを活用できます。最初の37%の候補(例:10個の製品のうち最初の3~4個)は購入せずに観察し、各商品の特徴や価格を比較します。観察期間後に最初の37%よりも良いと感じた商品が見つかれば、その商品を購入します。
- 美容室やクリニック探し
- 大学・スクールの選択 など
つまり、複数の選択肢から最良のひとつを選びたいときに、この考え方は強い味方になります。
選択肢が多すぎて決められないとき。理想が高くて前に進めないとき。そんなときに、「もう感情ではなく、理論で決めたい」と思ったら――この最適停止理論が、あなたの背中をそっと押してくれるかもしれません。
結論:感情を整え、タイミングを信じる“知的な恋愛”
最適停止理論が教えてくれるのは、「理想の高さ」を客観的に見つめ直し、冷静な“見極め期間”を設けることで、迷いや不安を減らしながら賢く決断できるということです。
誰と付き合えば幸せになれるのか、結婚すれば後悔しないのか。
そんな問いに感情だけで向き合うと、選択の迷路に迷い込みやすくなります。
でも、“感情”を一度横に置き、“理論”という地図を手にすれば、不安に振り回されずに、納得のいく一歩を踏み出せるはずです。
「いつ決めるべきか」「どこで踏み切るか」を理論的に理解すること。
それは、恋愛をもっと自由に、軽やかにする知的な武器になります。
迷う時間を減らして、育てる時間を増やす。
それが、本当に幸せなパートナーシップを築くための近道です。